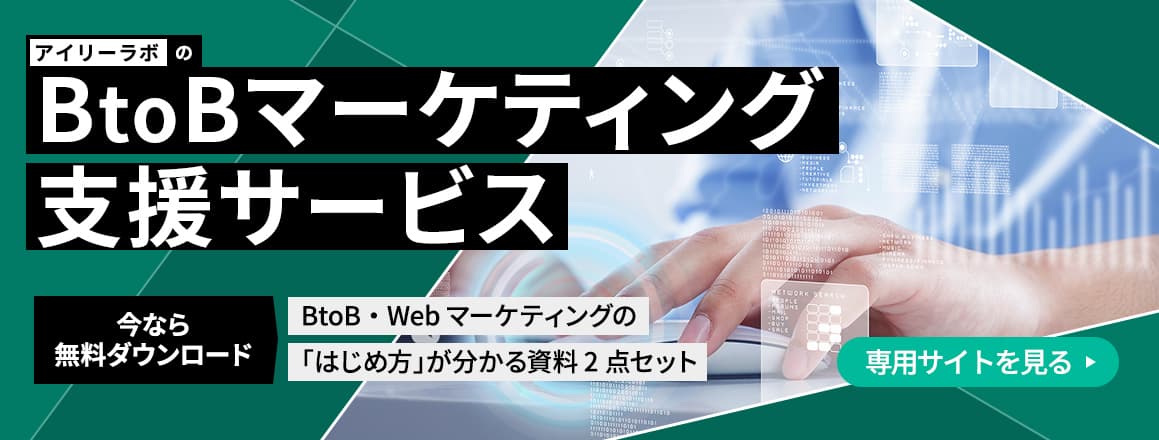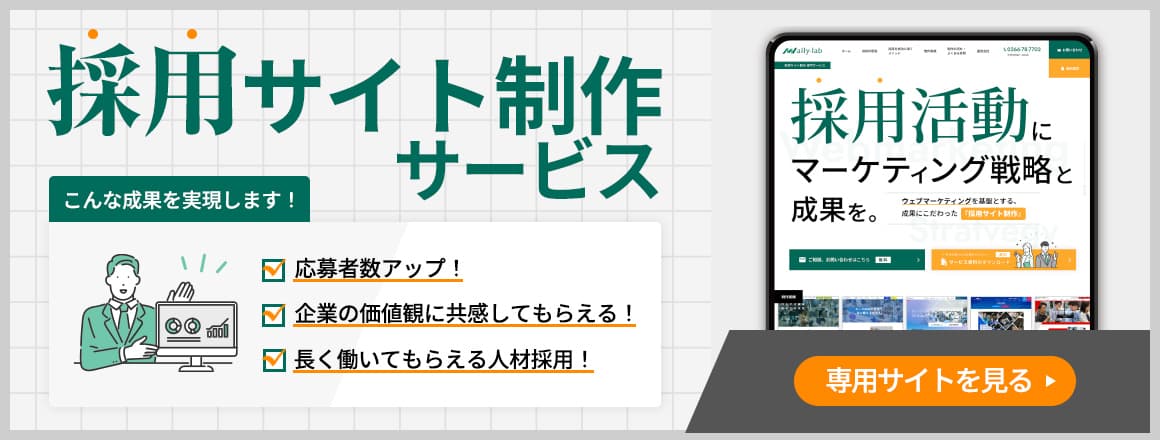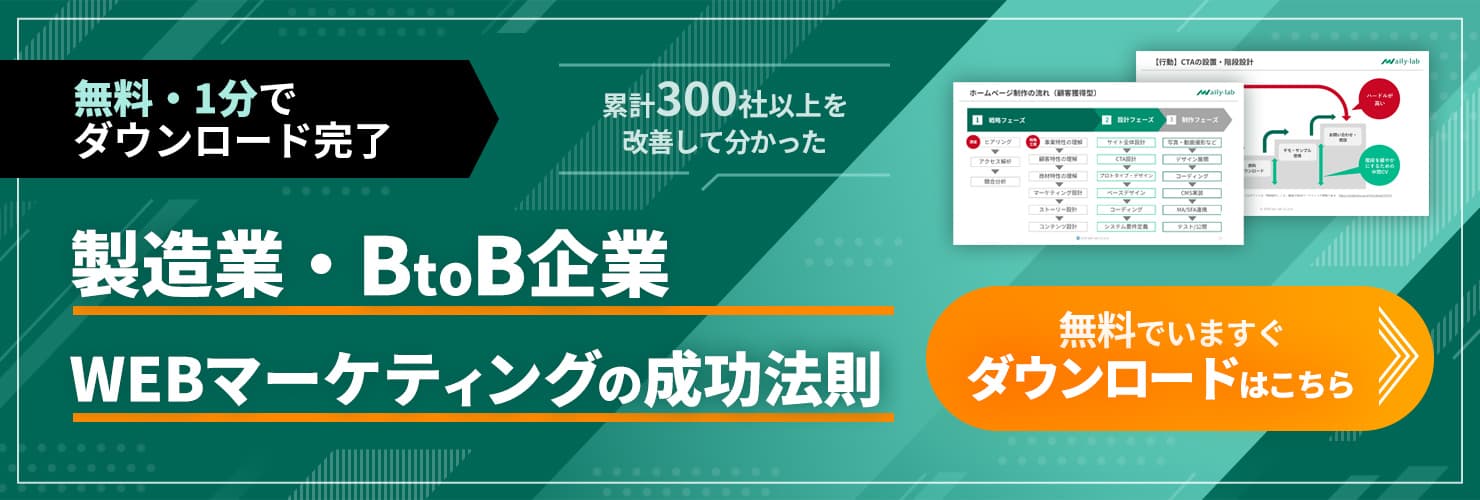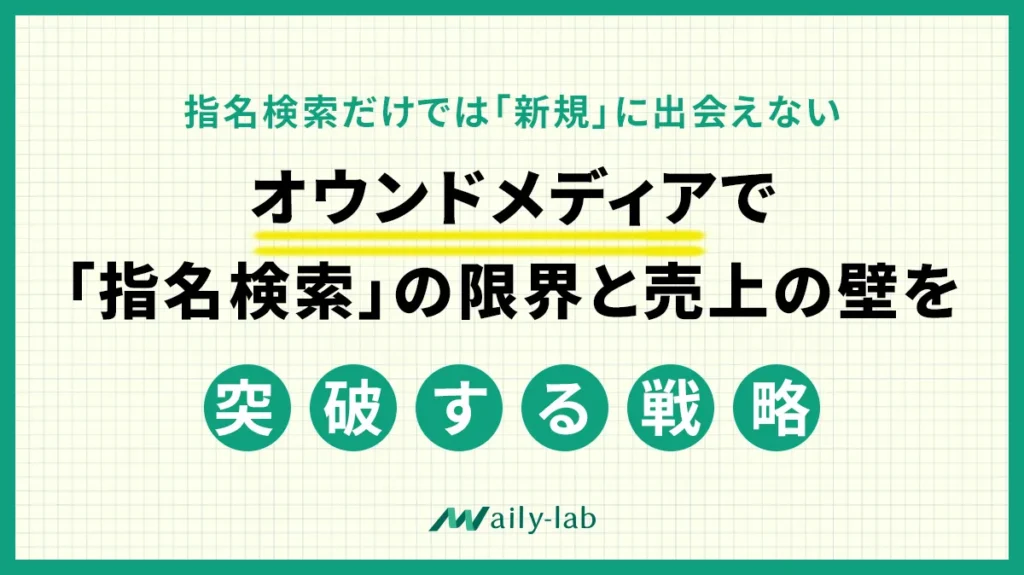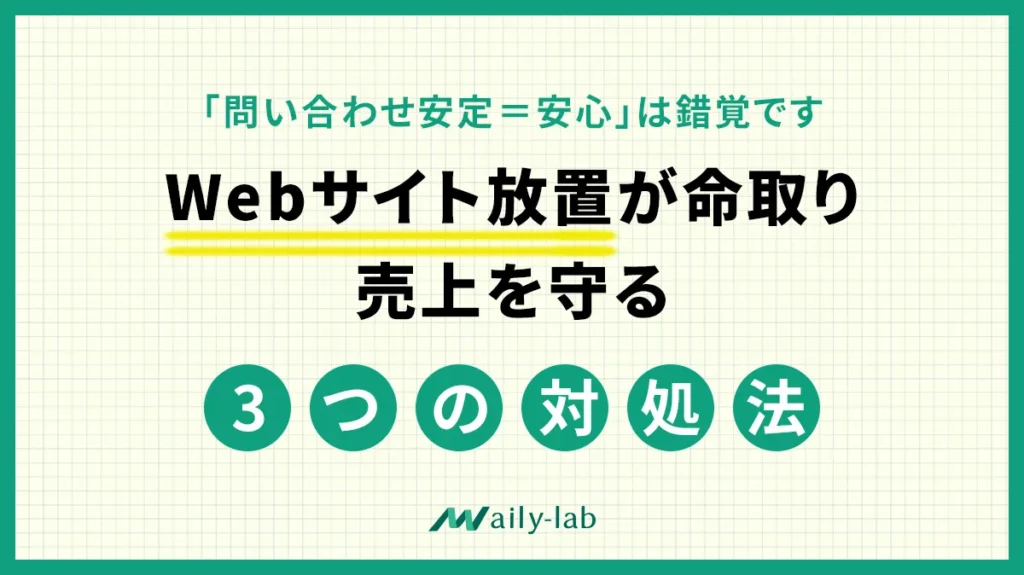【2025年最新版】ホームページ制作の費用相場ガイド!料金表と専門家の視点で解説

ホームページ制作の費用が10万円から数百万円以上と幅広く、自社にとっての適正価格が分からず悩んでいませんか。はじめに結論を述べると、制作費に固定の相場はありません。費用は「依頼先」「サイトの種類」「品質」という3つの要素で決まります。
この記事では、費用の構造や見積書の確認点、コストを抑える方法、そして維持費用や補助金制度の留意点について詳しく解説します。最後までお読みいただくことで、価格情報に惑わされず、自社の事業目標達成に繋がる「投資額」を見極めるための判断基準を理解できます。
目次
ホームページ制作の費用相場 早見表【2025年最新】

まず、様々な情報源のデータを統合した、現在の市場における費用相場の目安を「依頼先」と「サイトの種類」の2つの軸でご紹介します。ご自身の計画がどのあたりに位置するのか、大まかな全体像を掴んでください。
【依頼先別】費用相場一覧
依頼先は大きく4つに分類でき、それぞれに価格帯と特徴が存在します。
| 依頼先 | 制作費用の相場 | 特徴 |
| フリーランス・個人事業主 | 10万円 ~ 50万円 | 低コストな選択肢。柔軟な対応を期待できる一方、品質やサポート体制は個人のスキルに大きく依存します。 |
| 中小規模の制作会社 | 50万円 ~ 300万円 | 品質と価格のバランスが取れており、多くの中小企業にとって現実的な選択肢。組織的な対応を期待できます。 |
| 大手制作会社 | 300万円 ~ 1,000万円以上 | 高品質かつ戦略的なサイト構築ができます。大規模プロジェクトやブランディングを重視する場合に適しています。 |
| 自作 (CMS/作成ツール) | 初期費用 0円~ / 月額 2,000円~ | コストを最小限に抑えられますが、社内での作業時間や学習コストが発生します。デザインの自由度は低いです。 |
【サイトの種類・規模別】費用相場一覧
ホームページは、その目的や規模(ページ数)によっても費用が大きく変動します。
| サイトの種類 | 小規模 (~10ページ) | 中規模 (10~30ページ) | 大規模 (30ページ以上) |
| コーポレートサイト | 30万円~100万円 | 60万円~300万円 | 300万円~1,000万円以上 |
| 採用サイト | 15万円~50万円 | 50万円~150万円 | 150万円~ |
| ECサイト(ネットショップ) | 50万円~100万円 | 100万円~500万円 | 500万円~ |
| オウンドメディア | 30万円~100万円 | 100万円~300万円 | 300万円~ |
| LP (ランディングページ) | 10万円~60万円以上 | – | – |
上記の表は一般的な目安であり、実際の費用はデザインの質、機能の複雑性、コンテンツ(文章や写真)の提供元により変動する点にご留意ください。特に「規模」という言葉は曖昧で、ページ数が少なくても複雑な機能があれば費用は高額になります。
見積書の構成要素:ホームページ制作費用の内訳

「なぜその金額になるのか?」を深く理解するために、見積書に含まれる主要な項目を分解し、それぞれがどのような役割を担っているのかを詳しく見ていきましょう。費用は大きく分けて、制作時に一度だけ支払う「初期制作費用」と、サイトを維持するために継続的に発生する「運用・維持費用」の2種類があります。
初期制作費用:サイト公開までに支払うもの
ウェブサイトを立ち上げるまでに発生する一括の投資です。これらの項目を理解すると、各社の見積もりが何を価値として提供しているのか、その妥当性を判断しやすくなります。
ディレクション/プロジェクトマネジメント費
これは、プロジェクト全体の成功を左右する「司令塔」の役割を担う費用です。建築で言えば「設計士」や「現場監督」にあたる工程です。具体的には、お客様の事業内容や課題をヒアリングし、「誰に、何を伝え、どう行動してほしいか」というウェブサイトの根幹となる戦略を立案します。競合サイトの調査、ターゲットユーザーの分析、サイト全体の構造設計(サイトマップ作成)、各ページの設計図(ワイヤーフレーム作成)などが含まれます。
さらに、デザイナーやエンジニアといった専門スタッフをまとめ、スケジュール通りに品質を保ちながらプロジェクトを進行させる管理業務も担います。一般的に総額の10%~30%が目安とされますが、この費用を軽視したり、単に「管理費」として安く見積もる会社には注意が必要です。優れたディレクションは、目的がぶれない、手戻りのないスムーズな制作進行を可能にし、結果的に費用対効果の高いウェブサイトを実現します。
デザイン費
サイトの「顔」と「使いやすさ」を作る費用です。単に色や形を美しく整えるだけでなく、訪問者が情報を探しやすいか、直感的に操作できるかといったUI(ユーザーインターフェース)設計や、サイトを利用する中でユーザーが快適さや満足感を得られるかというUX(ユーザーエクスペリエンス)設計も含まれます。 費用は、既存のデザインの型(テンプレート)をベースにするか、企業のブランドイメージに合わせてゼロからオリジナルでデザインするかで大きく変わります。
テンプレートデザイン
費用を抑え、制作期間を短縮できます。相場は5万円~20万円程度です。
オリジナルデザイン
企業の独自性や世界観を表現でき、競合との差別化に繋がります。トップページは15万円~50万円以上、下層ページは1ページあたり3万円~10万円程度が相場となり、デザインの複雑性によって変動します。
コーディング/開発費
完成したデザイン画を、パソコンやスマートフォンなどのブラウザで実際に表示・操作できるように、HTML、CSS、JavaScriptといった専門言語を用いてプログラムを組んでいく作業費用です。 また、多くの企業が導入するCMS(コンテンツ管理システム)の構築もここに含まれます。CMSの代表格であるWordPressなどを導入すると、専門知識がない担当者でもブログやお知らせを簡単に更新できます。 現代では必須のスマートフォン対応(レスポンシブデザイン)もこの工程で実行しますが、パソコン用とスマートフォン用でレイアウトが崩れないように調整する手間がかかるため、費用に影響します。
コンテンツ制作費
サイトに掲載する文章(キャッチコピー、事業内容の説明文)、写真、動画、イラストなどの「中身」を作成・調達する費用です。多くの場合、これはオプション項目とされ、お客様側で原稿や写真を用意すると、コストを大幅に削減できます。 ただし、ターゲットに響く文章(SEOライティング)や、製品の魅力を最大限に引き出す高品質な写真は、サイトの成果を大きく左右する重要な投資でもあります。プロのライターやカメラマンに依頼する場合は、別途数十万円の費用がかかることも珍しくありません。特に製造業など専門性が高い分野では、技術的な内容を正確に伝えられるライターの存在が不可欠です。
システム実装費
お問い合わせフォームの設置はもちろん、ECサイトの決済機能、会員ログイン機能、製品検索システム、予約システムなど、ホームページに特定の機能を持たせるための費用です。機能が複雑になればなるほど、専門的な技術が必要となり、開発費は数十万円から数百万円に及ぶこともあります。
運用・維持費用:公開後にかかり続けるもの
ホームページは公開したら終わりではありません。むしろ公開してからがスタートです。物理的な店舗と同じように、家賃や光熱費のように維持・運営していくための継続的な費用が発生します。初期費用だけでなく、これらのランニングコストも長期的な視点で考慮して予算を組むことが求められます。
サーバー・ドメイン費
ホームページのデータを保管しておくインターネット上の「土地」にあたるのがサーバー、その土地の「住所」にあたるのがドメインです。これらがなければ、ホームページを世界中に公開し続けることはできません。サイトの規模や予想されるアクセス数によってサーバーの料金は変動しますが、一般的なコーポレートサイトであれば年間で1万円~3万円程度がひとつの目安です。
保守・管理費
サイトを24時間365日、安全かつ正常な状態に保つための「保険」のような費用です。具体的には、WordPressなどのCMS本体や、機能を追加する部品(プラグイン)の定期的なバージョンアップ、セキュリティの脆弱性を狙ったサイバー攻撃からの防御、万が一のデータ消失に備えたバックアップなどが含まれます。これを怠ると、ある日突然サイトが表示されなくなったり、ウイルスに感染して訪問者に被害を与えたり、顧客情報が漏洩したりする深刻な事態につながるリスクがあります。制作会社に依頼する場合、月額5,000円~5万円以上が相場です。
SSL証明書費
サイトの通信を暗号化(URLがhttps://で始まるもの)し、訪問者がお問い合わせフォームなどで入力した個人情報などを保護するための費用です。現在では企業の信頼性を示す上で必須の対応となっており、Googleも検索順位の評価要因としています。多くはサーバー費用に含まれていますが、より信頼性の高い企業認証SSLなどは別途費用が必要です。
マーケティング・SEO費
サイトの集客力を高め、ビジネスの成果に繋げるためのオプション費用です。検索結果で上位に表示させるためのSEOコンサルティングや、リスティング広告の運用代行、アクセス解析レポートの作成などが含まれます。これは事業成長のための重要な「攻めの投資」となり、費用は月額5万円から100万円以上と、施策内容によって大きく異なります。
運用・維持費用の相場まとめ表
| 項目 | 費用の目安 | 内容 |
| サーバー・ドメイン費 | 年間 1万円~3万円程度 | サイトのデータを保管する場所(サーバー)と住所(ドメイン)の利用料。 |
| 保守・管理費 | 月額 5,000円~5万円以上 | セキュリティ対策、ソフトウェアのアップデート、バックアップなどサイトを安全に保つための費用。 |
| SSL証明書費 | サーバー費用に含まれることが多い | 通信を暗号化し、訪問者の情報を保護するための費用。高レベルのものは別途費用が必要。 |
| マーケティング・SEO費 | 月額 5万円~100万円以上 | SEO対策や広告運用など、サイトの集客力を高めるための専門的な活動にかかる費用。 |
ホームページ制作費用を賢く抑える5つのコツ
予算には限りがある中で、効果的なホームページを作るための具体的な方法を5つご紹介します。これらを意識するだけで、数十万円単位でのコスト削減に繋がる可能性があります。
1. 目的を明確にし、優先順位をつける
「何のためにホームページを作るのか」を可能な限り具体的に、数値目標を交えて定義します。「月に20件の新規問い合わせを獲得する」「採用活動で年間5人の技術者に応募してもらう」「既存顧客への技術情報提供を効率化し、サポート部門の電話対応時間を15%削減する」など、具体的な目標を設定すると、本当に必要な機能やページが見えてきます。逆に目的が曖昧なままだと、「競合のサイトにあるから」「あった方が見栄えが良いから」といった理由で不要な機能を追加してしまい、結果的に高コストで効果の薄いサイトになってしまいます。
2. 小さく始めて大きく育てる
最初から全ての機能を盛り込んだサイトを目指す必要はありません。特に初めてホームページを作る場合や、リニューアルで何から手をつけていいか分からない場合は、MVP(Minimum Viable Product:実用最小限の製品)という考え方が有効です。まずは会社案内、事業内容、最低限の実績紹介、お問い合わせフォームといった、核となる情報に絞った小規模なサイトでスタートします。そして公開後に、アクセスデータや顧客からの反応を見ながら、ブログ機能(オウンドメディア)や詳細なサービスページ、採用特設ページなどを段階的に追加していく「成長させる」というアプローチです。これにより、初期投資を抑えつつ、本当に市場から求められているものにだけ投資できます。
3. 写真や文章はできるだけ自分で用意する
前述の通り、コンテンツ制作は費用を大きく左右する要因です。プロのカメラマンに撮影を依頼したり、ライターに原稿作成を依頼したりすれば品質は格段に上がりますが、その分費用も数十万円単位で増加します。最近ではスマートフォンのカメラ性能も非常に高くなっています。製品写真やスタッフ紹介の写真、工場内の風景などは、まず自社で撮影できないか検討します。同様に、事業内容の説明文や製品の技術的な解説、会社の沿革といった文章も、外部のライターよりも社内の担当者の方が、より正確で、情熱のこもった内容を書ける場合も多いです。事前に準備しておくべき素材リストを作成し、自社で対応できる範囲を明確にしておくだけで、制作会社との打ち合わせもスムーズに進みます。
4. デザインはテンプレートを活用する
ゼロからデザインを制作する「カスタムデザイン」は、企業の独自性やブランドイメージを細部まで表現できる一方で高コストになります。デザインに強いこだわりがなく、「まずは信頼感のあるしっかりとした見た目のサイトが欲しい」という場合は、既存のデザインの型(テンプレート)をベースに制作すると、開発期間を短縮し、費用を削減できます。多くの制作会社が、様々な業種に対応できる品質の高いテンプレートを複数用意しています。テンプレートをベースに、ロゴやメインカラー、主要な写真だけを自社のものに差し替えるだけでも、十分にオリジナリティのあるサイトを構築できます。
5. 複数の会社から相見積もりを取る
1社だけの見積もりで判断するのは危険です。同じ要件を伝えても、会社によって提案内容や金額は大きく異なります。必ず最低でも2~3社から見積もり(相見積もり)を取り、各社の提案内容と金額を比較検討します。
その際、単純な金額の安さだけで判断してはいけません。「なぜこの金額なのか」という内訳を丁寧に説明してくれるか、自社の業界やビジネスへの理解度は高いか、過去の制作実績は豊富か、そして担当者とのコミュニケーションはスムーズか、といった点も含めて総合的に判断することが、失敗しないパートナー選びの鍵となります。特に、極端に安い見積もりには注意が必要です。必要な工程が省略されていたり、公開後のサポートが全くなかったりするケースも少なくありません。
アイリーラボからのワンポイント解説
ホームページを「費用」と考えるか「投資」と考えるかで、かけるべき金額は違ってきます。
「費用」であれば、上記に挙げた工程をできるだけ安くする方法をおすすめします。
「投資」であれば、目的の最優先として「営業ツール」としてホームページが機能することが重要です。そのため、相見積で金額を比較するのはもちろんですが、各制作会社の特長や同じ業種での実績や成功事例、保有するノウハウなど、目的の達成実現性の観点からの比較検討が必要です。
ホームページ制作に使える補助金・助成金の活用と留意点
制作費用を抑える有効な手段として「補助金」の活用を検討する企業は多いですが、その利用には、しばしば見過ごされがちな重大な注意点があります。これを理解せずに計画を進めると、かえって資金繰りを悪化させる可能性もあるため、必ず内容を正確に把握してください。
主要な補助金の紹介
中小企業がホームページ制作で活用できる可能性のある代表的な制度には、以下のようなものがあります。
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者の販路開拓や生産性向上を支援する制度。ホームページ制作は「販路開拓」のための「広報費」として計上できるため、汎用性が高く最も活用しやすい補助金の一つです。ただし、単にサイトを作るだけでは不十分で、そのサイトを使ってどのように販路を開拓していくのかという具体的な事業計画が求められます。
IT導入補助金
業務効率化やDX(デジタルトランスフォーメーション)推進を目的としたITツール導入を支援する制度。注意点として、単なるコーポレートサイト制作は対象外となることが多く、EC機能や予約機能、顧客管理システムといった、特定の業務プロセスを効率化する機能を持つサイトが対象となる傾向があります。
事業再構築補助金
新分野展開や事業転換、業種転換など、思い切った事業再構築を行う企業を支援する制度。通常のサイト制作やリニューアルは対象外ですが、Webサイトが全く新しい事業(例:製造業者が新たにオンライン直販事業を始める際のECサイト構築など)の中核をなす場合に活用できる可能性があります。
地方自治体の補助金
都道府県や市区町村が独自に設けている制度です。国の制度よりも要件が緩やかであったり、地域の実情に合っていたりする場合が多く、見逃せません。まずは自社が所在する自治体の商工課などのウェブサイトを確認し、利用できる制度がないか調査することが推奨されます。
補助金活用で留意すべき3つの点
補助金制度の活用を検討する上で、以下の3点は資金計画に関わるため、必ず押さえておきます。
1. 補助金は原則として「後払い」
これが最も理解しておくべき点です。補助金は、事業者がまず制作費用の全額を自己資金で制作会社に支払い、事業が完了した後に実績報告書などを提出し、審査を経て初めて交付されます。 つまり、手元に制作費用全額の資金がなければ、この制度は利用できません。「補助金が採択されたから、そのお金で支払おう」という計画は成り立たないのです。
2. 不採択のリスク
申請すれば必ず採択されるわけではありません。説得力のある事業計画書の提出が求められ、審査の結果、不採択となるケースも少なくありません。制度によっては採択率が50%を下回ることもあり、「補助金ありき」で資金計画を立てるのは危険です。必ず、補助金がなくても事業を遂行できる資金計画を立てる必要があります。
3. 契約タイミングの厳格なルール
補助金の交付が決定する「採択通知」を受け取る前に、制作会社と契約・発注をしてはいけません。採択前に発生した費用(発注、支払いなど)は、原則として補助対象外となります。必ず「交付決定日以降」に契約・発注を行うというルールを遵守します。
これらの注意点からわかるように、補助金は資金繰りに窮する企業のための救済措置ではなく、財務的に健全な企業が、計画していた投資のコストを低減させたり、成長を加速させたりするための「戦略的ツール」と捉えるべきです。
アイリーラボからのワンポイント解説
2025年現在、単純にホームページを作るだけですと補助金は受けにくく、上限金額が小さいなど申請の費用対効果が低いです。
例えば、顧客管理システムやECと連携するなど一つ上の活用が見込まれるもので申請することが有効です。
そういった要件がない場合は、人材採用に絡めた補助金の活用や上記に挙げた以外の各市町村などの補助金などは申請が比較的簡単なのでおすすめです。
まとめ:最適なホームページは「コスト」ではなく「投資」で考える
今回は、ホームページ制作の費用相場について、その内訳から価格を左右する要因、費用を抑えるコツ、そして補助金活用の注意点まで、幅広く、そして深く解説しました。
本記事の要点を振り返りましょう。まず、ホームページ制作に固定の相場はなく、費用は依頼先、サイトの種類・規模、品質という3つの要素で決まることを解説しました。そして、見積もりを確認する際は「初期費用」だけでなく、サーバー代や保守費といった「運用・維持費用」も長期的な視点で考慮することが重要です。費用を抑えるためには、サイトの目的を明確にし、自社で素材を準備するなど、できる範囲を増やすことが有効な手段となります。また、補助金は「後払い」かつ「不採択リスク」があることを理解し、戦略的に活用することが求められます。
様々な価格情報が溢れる中で、「いかに安く作るか」という視点に陥りがちです。しかし、最も考慮すべきは、そのホームページが貴社の事業目標達成にどれだけ貢献してくれるかという「投資対効果(ROI)」の視点です。
100万円かけて作ったサイトが年間300万円の利益を生み出すのであれば、それは成功した「投資」です。一方で、10万円で作ったサイトが全く問い合わせに繋がらず、誰にも見られないのであれば、それは残念ながら失敗した「コスト」になってしまいます。この記事が、貴社にとって最適なホームページという「賢い投資」を行うための一助となれば幸いです。まずは、「自社はホームページで何を達成したいのか?」という事業目標を具体的に書き出すことから始めてみてください。それが、成功するホームページ制作の第一歩です。
無料相談・資料ダウンロード
contact・download
Webマーケティング、Webサイト制作・運用のご相談は、
aily-lab アイリーラボ へお気軽にお問い合わせください