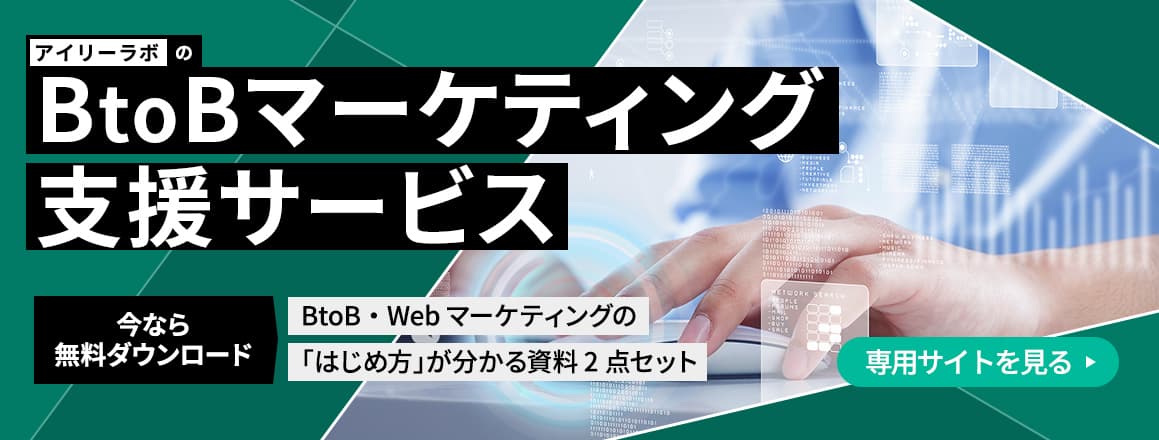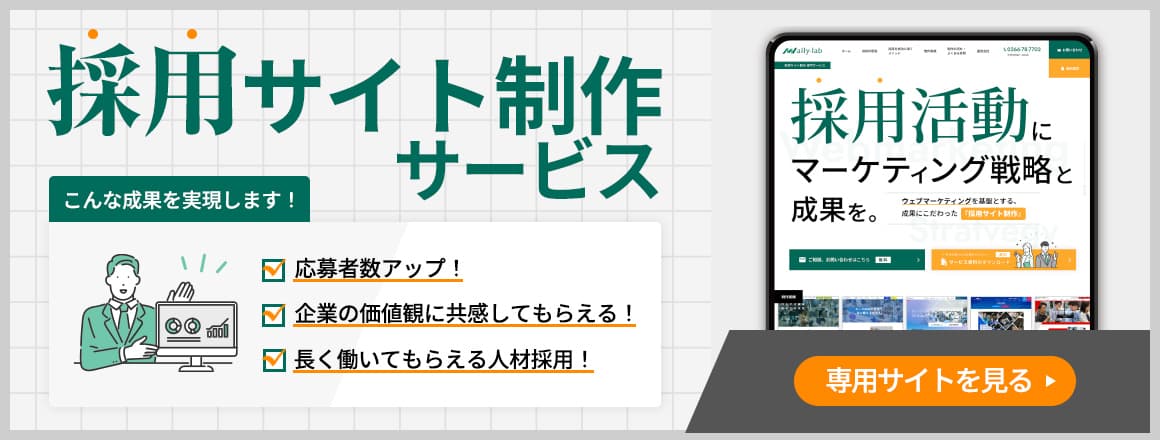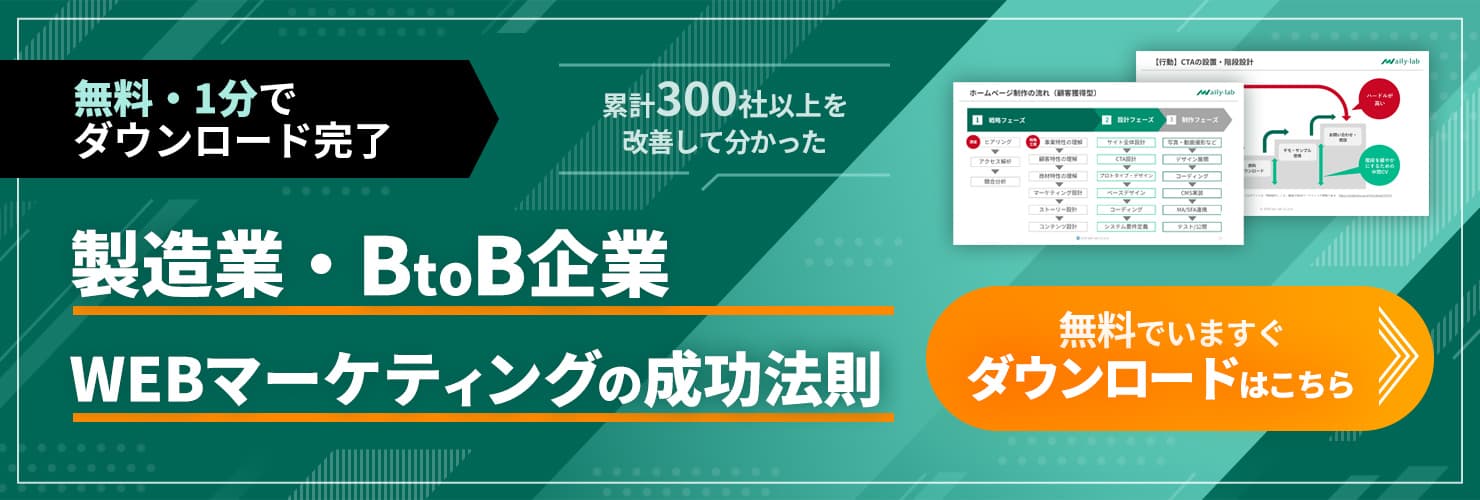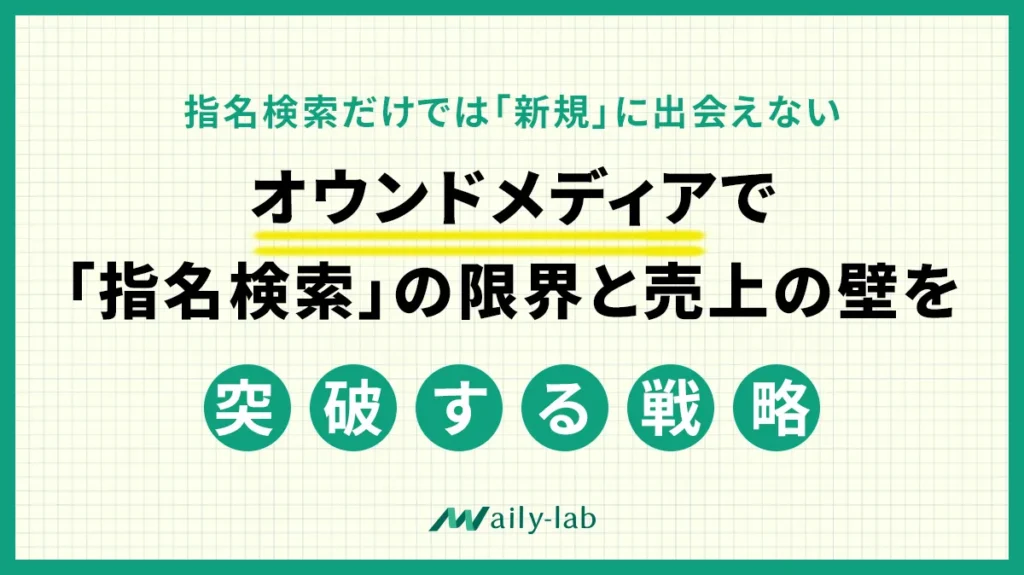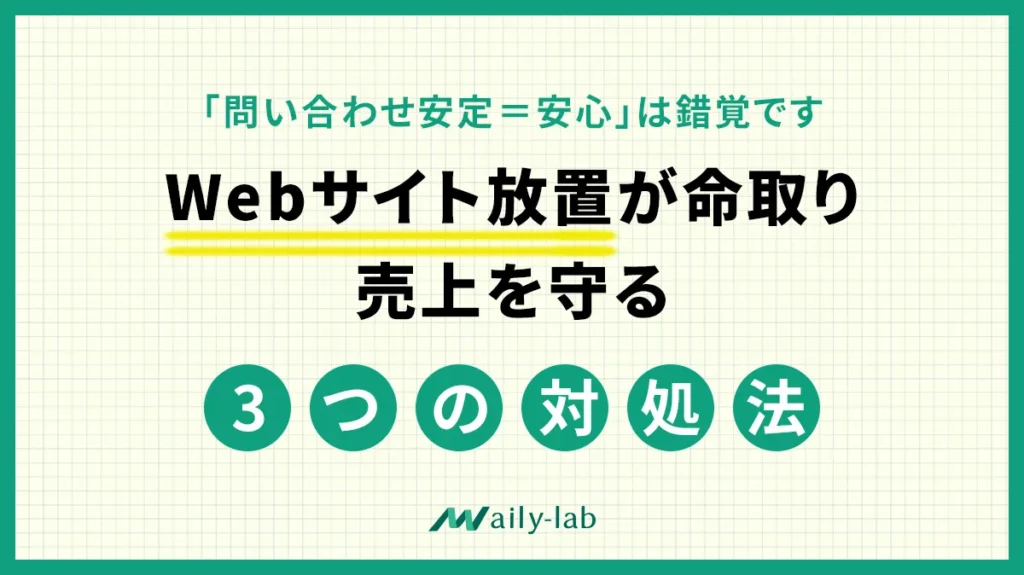【2025年最新】中小企業のホームページ制作ガイド|失敗しない会社の選び方から費用相場までプロが解説
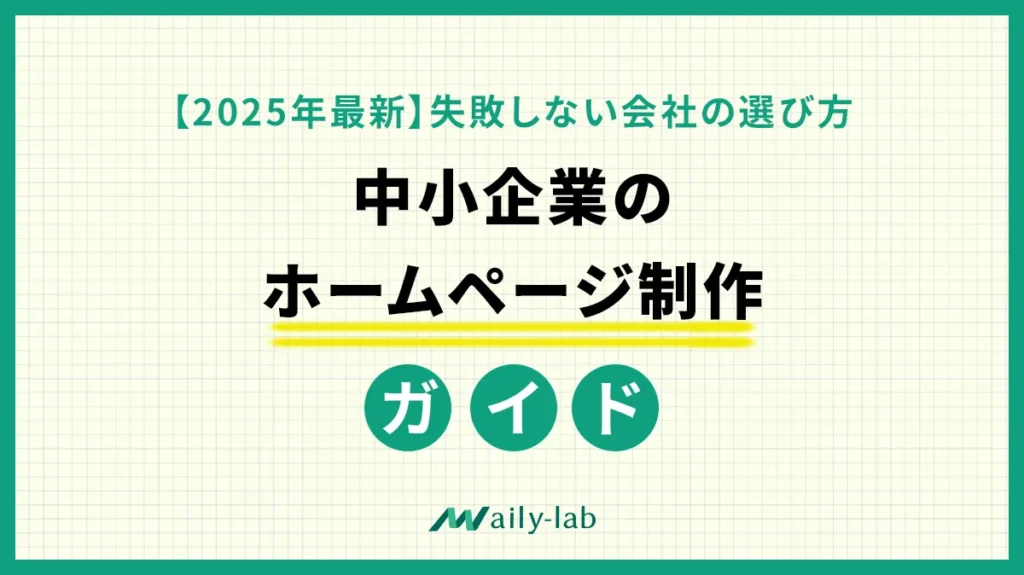
「Webからの問い合わせを増やしたいが、どこに頼めばいいかわからない…」そんなお悩みはありませんか?中小企業のホームページ制作の成否は、最適なパートナーを見極められるかで9割決まります。Webサイトは今や、売上や採用に直結する「戦略エンジン」です。価格やデザインだけで選んで失敗する例は後を絶ちません。この記事ではプロが、目的設定から費用相場、そして最も重要な「失敗しない制作会社の見極め方」まで、具体的な手順を網羅的に解説します。
目次
【大前提】ホームページ制作で失敗する前に知るべき3つの視点
具体的なステップに入る前に、まず大前提として知っておくべき3つの重要な視点があります。これを知らずに進めると、プロジェクトが思わぬ方向へ進んでしまう危険性があるため、必ず押さえておきましょう。
視点1:ホームページは「作ること」がゴールではない
最もよくある失敗は、ホームページを「作ること」自体をゴールにしてしまうことです。新しいウェブサイトが完成する高揚感が、本来の目的を見失わせてしまうのです。しかし、本来の目的はそこにはありません。
- 見込み顧客から月10件の問い合わせを獲得する
- 新卒採用の応募者数を前年比20%増やす
- 特定の製品・サービスのブランド認知度を高める
このように、ホームページ制作はあくまで事業課題を解決するための「手段」です。Webサイトが公開された日は、ゴールではなくスタートライン。そこからいかにして事業成果を生み出していくかが、真の成功と言えます。この視点が抜けていると、ただ綺麗なだけの「置物」のようなサイトが完成してしまいます。
視点2:あなたが必要なのは「実行者」? それとも「戦略家」?
ホームページ制作会社は、大きく2つのタイプに分かれます。この違いを理解することが、パートナー選びの第一歩です。
- 実行者(インプリメンター):依頼側の明確な指示や計画に基づき、それを忠実に、高品質かつ迅速に形にする制作会社。テンプレートなどを活用し、比較的低コストで制作できることが多いです。
- 戦略家(ストラテジスト):事業目標の達成という上流工程から伴走し、Web戦略の立案、サイト設計、公開後の改善サイクルまでを主導する制作会社。コンサルティング要素が強く、経営的視点からの提案が期待できます。
もし、あなたに「こういうサイトを作ってほしい」という明確な計画があるなら、優秀な「実行者」が必要です。一方で、「Webで成果を出したいが、どうすればいいか分からない」という状況であれば、共に計画を練ってくれる「戦略家」を探すべきです。この自社の状況分析を怠ると、「言われたことはやってくれるが、成果につながる提案がない(実行者に戦略を求めたケース)」あるいは「提案ばかりで費用がかさみ、なかなか形にならない(戦略家に実行だけを求めたケース)」といったミスマッチが生じます。
視点3:見落としがちな「総所有コスト(TCO)」を意識する
ホームページの費用は、初期制作費だけではありません。公開後もサーバー代やドメイン代、保守費用、コンテンツの更新費用などが継続的に発生します。これらの運用コストまで含めた「総所有コスト(Total Cost of Ownership)」で予算を考えなければ、「初期費用は安かったのに、年間の維持費が思ったより高額になってしまった」という事態に陥ります。
特に保守契約は重要です。月額費用がかからないプランは一見魅力的に見えますが、それは「何かあったらその都度見積もり」という取引型の関係です。一方、月額の保守契約を結ぶプランは、サイトの安定稼働や継続的な改善提案まで責任を負うパートナーシップ型の関係と言えます。社内にWebの専門知識があるかないかで、どちらが長期的に見て価値が高いかは大きく変わってきます。セキュリティのアップデートや軽微な修正、定期的なバックアップなど、目に見えにくいですが事業継続に不可欠な作業が含まれているかどうかも確認すべき重要なポイントです。
アイリーラボからのワンポイント解説
私たちのこれまでの経験では、多くの企業が制作に注力する傾向が強く、公開後の運用について考えを持っていないことが多いです。
ホームページを作るだけであれば、その後は維持やメンテナンス程度で良いでしょう。
しかし、成果を上げるためにホームページを作るのであれば、公開後は分析や改善といった活動が必要になるので、長期的な投資も予算に見込む必要があります。
最近では、競合他社も同じようにホームページに力を入れているわけなので、公開して一時期成果が上がったとしても、時間が経つに連れて成果が落ちることが多々あります。
運用費用は継続的に発生するものなので、成果への投資として毎年の予算に盛り込むことをおすすめします。
【STEP1】目的を明確にする:なぜホームページを作るのか?
成功するホームページ制作は、明確な目的設定から始まります。「なぜ、ホームページを作るのか?」この問いに、具体的かつ明確に答えられるようにしましょう。
目的の具体例
中小企業がホームページを持つ目的は多岐にわたりますが、主に以下の4つに分類されます。自社が最も重視するのはどれか、優先順位をつけましょう。
見込み顧客の獲得、問い合わせ増加
- 製品やサービスに関する問い合わせフォームを設置し、新規の商談機会を創出する。
- お役立ち情報(ブログや導入事例)を発信し、潜在的な顧客を集める。単なる問い合わせだけでなく、「質の高い」見込み客からのアプローチを増やすことも重要な目的です。
人材採用の強化
- 企業のビジョンや社風、社員インタビューなどを掲載し、求職者に魅力を伝える。
- エントリーフォームを設置し、応募のハードルを下げる。特に専門職の採用では、技術的な取り組みや開発環境を発信することが有効です。
企業の信頼性・ブランド価値の向上
- プロフェッショナルなデザインで、企業の信頼性を高める。
- 事業内容や実績、会社概要を正確に伝え、取引先や金融機関からの信用を得る。IR情報や品質管理体制の開示も含まれます。
業務効率化
- 「よくある質問」ページを作成し、電話やメールでの問い合わせ対応工数を削減する。
- 製品カタログやマニュアル、仕様書などをダウンロードできるようにし、資料送付の手間を省く。
目標数値(KGI/KPI)を設定する
目的を明確にしたら、それを測定可能な数値目標に落とし込みます。これにより、ホームページへの投資対効果(ROI)を客観的に評価し、データに基づいた改善のアクションに繋げることができます。「なんとなくアクセスが増えた」で終わらせないことが重要です。
| 目的の例 | KGI(最終目標指標)の例 | KPI(中間目標指標)の例 |
| 見込み顧客の獲得 | 月間の問い合わせ件数:10件 | 問い合わせページの閲覧数、関連キーワードでの検索順位、資料ダウンロード数 |
| 人材採用の強化 | 年間の採用応募者数:前年比20%増 | 採用ページの閲覧数、エントリーフォームの入力完了率、説明会への申込数 |
| ブランド価値の向上 | 特定製品名の指名検索数:半年で2倍 | サイト全体のアクセス数、SNSでの言及数、主要ページの平均滞在時間 |
ターゲットを設定する
「誰に、何を伝えたいのか?」を具体化することも重要です。ターゲットユーザーの人物像(ペルソナ)を詳細に設定することで、心に響くコンテンツやデザインの方向性が定まります。
ターゲット設定の例(製造業)
- 役職: 製造業の購買担当者、設計開発担当者
- 年齢: 30代~50代
- 情報収集の方法: 業界専門誌、Web検索(技術的なキーワード)、展示会
- 抱えている課題: 「コストを抑えつつ、品質の高い部品を探している」「特定の技術要件を満たす加工先が見つからない」
- サイトに求める情報: 技術的な強み、加工事例、品質管理体制、設備一覧、見積もり依頼のしやすさ
特にBtoBでは、情報を探す「担当者」と、最終的な決裁を下す「決裁者」では求める情報が異なります。担当者は技術的な詳細やスペックを、決裁者は導入実績や費用対効果を重視する傾向があります。両者のニーズに応えるコンテンツを用意し、サイト内でスムーズに回遊できるような設計が求められます。
アイリーラボからのワンポイント解説
BtoB中小企業のWebコンサルティングの経験上WebサイトのKGI/KPIの設定は、
KGI・・・ホームページからのお問い合わせ数、売上げ
KPI・・・ホームページのアクセス数、コンバージョン率
を軸とすることが多いです。
あとは、アクセス数の流入がどのように構成されているか?(例:有料検索、無料検索、リンク、メールマガジンなど)
【STEP2】費用相場を知る:いくらかかるのか?
ホームページ制作にかかる費用は、その規模や機能によって大きく変動します。自社の目的と予算に合った価格帯を把握しましょう。
価格帯別の特徴
| 価格帯 | 特徴 | メリット | デメリット |
| エントリー(~30万円) | テンプレートを活用した小規模サイト(5~10ページ程度)。名刺代わりの基本的な企業サイト。 | 低コスト、短納期(1ヶ月程度)で公開できる。 | デザインの自由度が低い。戦略的なコンサルティングは含まれないことが多い。SEO対策も基本的なものに限られる。 |
| ミッドレンジ(30万~150万円) | オリジナルデザインでのカスタムメイド。中小企業で最も一般的な価格帯。戦略的なコンテンツ企画や基本的なSEO対策を含む。 | デザインの独自性、戦略的要素、コストのバランスが良い。事業内容に合わせた柔軟な設計が可能。 | 制作に2~4ヶ月程度の時間がかかる。要件定義が曖昧だと追加費用が発生しやすい。 |
| プレミアム(150万円~) | 大規模な事業変革プロジェクト。オウンドメディア構築や詳細なブランディング戦略、システム連携などを含む。 | 包括的なデジタル戦略そのものを納品物として得られる。高い成果が期待できる。 | 高額な投資が必要。制作会社との深いコミットメントと長期的な関係性が求められる。 |
費用の内訳
初期制作費以外にも、以下のような費用が発生することを念頭に置いておきましょう。
- サーバー・ドメイン費用: 年間1万円~数万円程度。サイトを公開し続けるために必須の費用です。
- 保守管理費用: 月額5,000円~5万円程度。システムのアップデートやセキュリティ対策、バックアップなどが含まれます。
- コンテンツ更新費用: 更新の都度見積もり、または保守契約に一定の作業時間が含まれる場合があります。
- その他: SSL証明書費用、Web広告の出稿費用、有料の写真・動画素材費、プラグイン等のライセンス費用など。
補助金の活用も視野に
ホームページ制作には、「IT導入補助金」や「小規模事業者持続化補助金」などの公的な補助金を活用できる場合があります。これらの補助金は、ITツール導入による生産性向上などを目的としており、ホームページ制作も対象となることが多いです。申請には要件や期間、事前の計画書提出などが必要なため、検討している場合は早めに公式サイトで最新情報を確認し、準備を進めましょう。
【STEP3】制作会社の選び方:どこに頼むべきか?
ここが最も重要なステップです。以下のポイントを参考に、自社にとって最適なパートナーを見極めましょう。
比較検討の5つのポイント
1.実績と事例
デザインの好みだけで選ぶのは危険です。「自社と同じ業界」や「自社が抱える課題と同じ課題を解決した」実績があるかを確認しましょう。その際、ただ綺麗なサイトを見るだけでなく、そのホームページがどのような成果(問い合わせ増、売上増など)をもたらしたのかという結果まで確認することが重要です。特にBtoB企業であれば、BtoBマーケティングの知見があるかは必須の判断基準になります。
2.得意分野(会社のDNA)
制作会社が提供している「ホームページ制作以外のサービス」に、その会社の本来の専門性、すなわち「DNA」が表れます。自社の目的に合わせて、最適なDNAを持つ会社を選びましょう。
集客・SEO特化型(マーケティングDNA)
- 特徴: Web広告運用代行やSEOコンサルティングも提供している。
- 見極め方: Webサイトを「見込み顧客獲得マシーン」と捉え、データに基づいた具体的な集客戦略を提案してくる。
- どんな企業におすすめ?: 「Webからの問い合わせを増やしたい」「広告費をかけずに集客したい」企業。
デザイン・ブランディング特化型(デザインDNA)
- 特徴: ロゴやパンフレットなど、紙媒体のデザインも手掛けている。
- 見極め方: Webサイトをブランドの世界観を表現する「メディア」と捉え、ビジュアルの一貫性やユーザー体験(UX)を重視する。
- どんな企業におすすめ?: 「ブランドイメージを刷新したい」「競合との差別化を図りたい」企業。
ITインフラ・サポート特化型(インフラDNA)
- 特徴: サーバー管理やOA機器、社内ネットワーク構築なども提供している。
- 見極め方: Webサイトをオフィス全体のIT環境の一部と捉え、セキュリティや安定稼働、業務連携を重視する。
- どんな企業におすすめ?: 「Web担当者がおらず、IT全般を相談したい」「長期的に安心して任せたい」企業。
3.サポート体制
公開後のサポート体制は必ず確認しましょう。「月額0円」を謳う会社は、更新や修正が発生するたびに見積もりが必要な「取引型」です。一方、「月額保守契約」が前提の会社は、継続的にサイトの面倒を見てくれる「パートナーシップ型」です。社内にWeb担当者がいない場合は、後者のほうが長期的に見て安心できるケースが多いです。
4.コミュニケーション
担当者との相性はプロジェクトの成否を左右します。無料相談などを活用し、以下の点を確認しましょう。
こちらのビジネスを深く理解しようと、多くの質問をしてくれるか?
専門用語を避け、分かりやすい言葉で説明してくれるか?
レスポンスは迅速で丁寧か?
デザイナーや開発者など、実際に手を動かす「制作者」と直接話す機会はあるか?(伝言ゲームによる意図のズレを防ぐため)
5.見積もりの妥当性
必ず2~3社から相見積もりを取りましょう。その際、単に総額を比較するのではなく、「作業項目」が詳細に記載されているかを確認します。「ホームページ制作一式」のような大雑把な見積もりを出す会社は注意が必要です。各項目がなぜ必要なのか、納得できる説明を求めましょう。極端に安い見積もりは、戦略設計やテスト工程など、目に見えないが重要な部分が省略されている可能性も疑うべきです。
アイリーラボからのワンポイント解説
中小企業のホームページ制作において、特に注視すべきポイント
中小企業ホームページ制作の成功の鍵は「デザイン」ではなく「自社の取るべき戦略」です。中小企業がデザイン良く飾ったところで、お問い合わせは増えません。見るべきは制作会社の「課題解決力」です。
また、制作会社が事例として出してくるデザインの良いホームページを見るといいなと思うかもしれませんが、最も陥りやすい失敗が「デザイン」の良し悪しは最も騙されやすい簡単な方法であることです。
本質的に成果を追い求めるのであれば下記のポイント、デザインのように表面に現れにくいものを見る必要があります。
・自社と同じ業界の実績の有無、成功事例などがあるか
・(実績がない場合でも)目的を達成するために再現性のあるノウハウや手法を持っているか
・自社の目的や課題を解決するための具体的な方法を提案できるか
・実績が豊富か
【STEP4】タイプ別・中小企業におすすめのホームページ制作会社
ここでは、前述した制作会社のタイプ別に、実績のある代表的な会社を紹介します。自社の目的と照らし合わせながら、相談先の候補として参考にしてください。
集客・SEOに強い制作会社の例
株式会社アイリーラボ

BtoB製造業に特化し、「成果を出す」ことにこだわるWeb制作を提供。マーケティング戦略の策定から伴走支援まで一貫して行い、集客できるサイト構築に強みを持つ。
キオミル株式会社

「課題解決型Web制作」を掲げ、BtoBマーケティング支援や本質的なSEO対策に強みを持つ。
デザイン・ブランディングに強い制作会社の例
株式会社スーパーグラフィックス

Webとグラフィックを横断する一貫したビジュアル・ブランディング戦略の構築を得意とする。
株式会社くえり
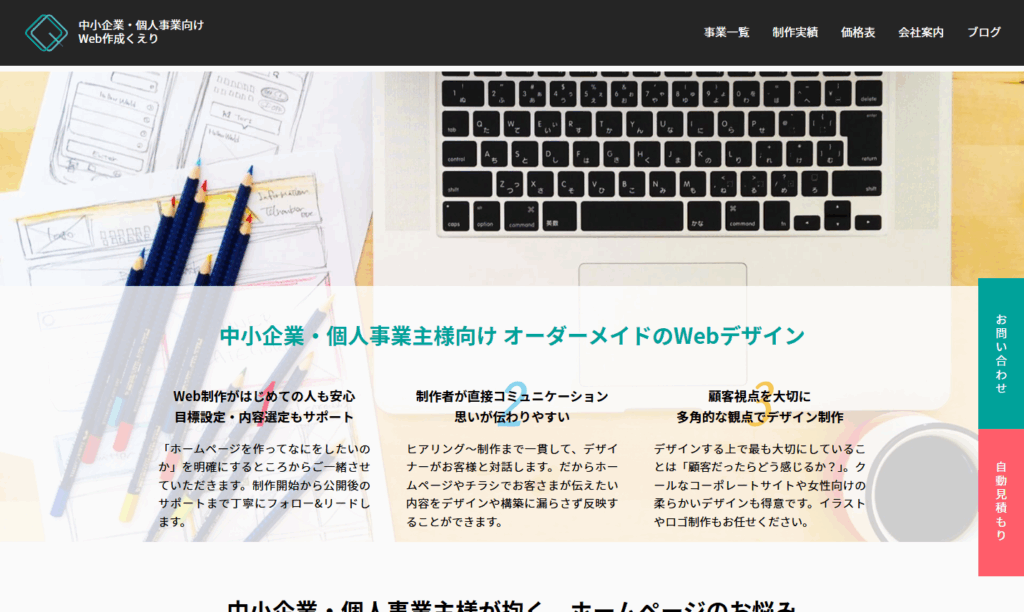
顧客の想いを形にする「翻訳者」的な役割を担い、ターゲットに合わせた多様なデザインテイストに対応。
実績豊富でサポートが手厚い制作会社の例
スターティア株式会社

上場企業グループとしての信頼性と組織的なサポート力が強み。法人利用に特化した独自CMSも提供。
株式会社リンク

ホームページ制作だけでなく、OA機器やテレワーク環境構築など、オフィス全体のITインフラをワンストップでサポート。
【STEP5】制作の基本的な流れ
実際に制作会社に依頼した場合、どのようなプロセスで進むのかを把握しておきましょう。この流れを理解しておくことで、各フェーズで自社が何をすべきかが明確になります。
1.ヒアリング・要件定義
制作会社があなたの事業内容、課題、ホームページの目的などを詳細にヒアリングします。この工程が最も重要です。自社の課題や要望を包み隠さず伝えましょう。
2.企画提案・見積もり
ヒアリング内容に基づき、制作会社がサイトの構成案や戦略、スケジュール、見積もりを提案します。提案内容が自社の目的と合致しているか、費用対効果は見合っているかを吟味します。
3.サイト設計
提案内容に合意後、サイト全体の構造を示す「サイトマップ」や、各ページのレイアウト設計図である「ワイヤーフレーム」を作成します。ユーザーが迷わず目的の情報にたどり着けるか、この段階でしっかり確認します。
4.デザイン・コンテンツ制作
ワイヤーフレームを基に、サイトのビジュアルデザインを作成します。並行して、サイトに掲載する文章や写真、図などのコンテンツを準備します。原稿や写真素材の準備は、依頼者側で行う作業が多く発生する工程です。
5.開発・コーディング
決定したデザインを、Webブラウザで表示できるようにプログラミング(コーディング)します。WordPressなどのCMS(更新システム)の組み込みもこの段階で行います。
6.テスト・公開
完成したサイトが様々な環境(PC、スマホ、各種ブラウザ)で正しく表示・動作するかをテストし、問題がなければサーバーにアップロードして公開します。誤字脱字の最終チェックもここで行います。
7.運用・改善
公開後は、アクセス解析を行いながら効果を測定し、定期的にコンテンツの更新や改善(PDCAサイクル)を行っていきます。公開がゴールではなく、ここからが本当のスタートです。
【独自性】他社サイトと差をつけるための3つの追加要素
多くの競合サイトが見落としがちな、独自性を高めるためのポイントを3つ紹介します。これらを取り入れることで、ユーザーからの信頼をさらに獲得できるでしょう。
セキュリティ対策の明示
「SSL/TLS(通信の暗号化)」の導入は今や常識ですが、それ以外にもプライバシーポリシーの整備や、使用しているシステムのセキュリティ対策について明記することで、顧客は安心して問い合わせや個人情報の入力ができます。特にBtoB取引では、セキュリティへの意識が企業の信頼性に直結します。サイトがどのように顧客情報を保護しているかを明確に示すことは、見えない部分での大きな差別化要因となります。
動画コンテンツの活用
製品の動作デモ、工場の様子、技術者のインタビューなど、テキストや写真だけでは伝わりにくい情報を動画で伝えることは非常に効果的です。特に複雑な技術や製品を持つ製造業にとって、動画は顧客の理解を深める強力なツールとなります。また、動画はページの滞在時間を延ばす効果もあり、これはSEOにおいても良い影響を与える可能性があります。
スマートフォン・タブレットへの完全対応
BtoBの担当者も、移動中や出先でスマートフォンを使って情報収集をします。PCサイトをただ縮小表示するだけでなく、スマホでの閲覧・操作に最適化された「レスポンシブデザイン」を徹底することで、機会損失を防ぎます。Googleが検索順位の評価基準としてモバイルサイトを主に見る「モバイルファーストインデックス」を採用している現在、これはユーザビリティだけでなく、SEOの観点からも必須の対策です。ボタンの大きさや文字サイズなど、細部への配慮がユーザー体験を大きく向上させます。
まとめ
本記事では、中小企業がホームページ制作で失敗しないための具体的なステップと視点を解説してきました。最後に、最も重要なポイントを振り返ります。
- 目的を明確にする: ホームページは「事業成果を出すための手段」であり、制作がゴールではない。
- 自社の状況を知る: 必要なのは、指示通りに作る「実行者」か、戦略から考える「戦略家」かを見極める。
- 会社のDNAを見抜く: 集客、デザイン、サポートなど、制作会社の得意分野と自社の目的を合致させる。
- 総所有コストで判断する: 初期費用だけでなく、公開後の運用コストまで含めて予算を考える。
ホームページ制作は、企業の未来への重要な投資です。この記事を参考に、ぜひ貴社にとって「最高」ではなく「最適」なパートナーを見つけ出し、事業成長を加速させるホームページ制作を成功させてください。
無料相談・資料ダウンロード
contact・download
Webマーケティング、Webサイト制作・運用のご相談は、
aily-lab アイリーラボ へお気軽にお問い合わせください